ストーリーと絵本構成EADLINE
| 1.シーン割り | 2.ダミー本 |
創作のはじめに
手作り絵本は、作ること自体が楽しければそれで良い、とも思えます。
でも、せっかく作るのだから、できるだけ完成度の高いものを作りたいですよね。
少々面倒なことも言っていますが、好きな絵本を思い浮かべて、
説明を読んでいただくと、分かりやすいかも知れません。
私が絵本講座で行っている方法を紹介します。
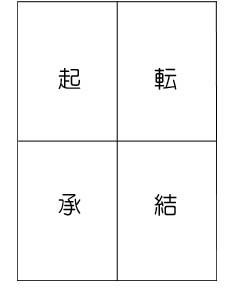
A4のコピー用紙を4つに折って、図のように配分します。
「起」は、話の発端です。物語の舞台や登場人物の紹介など、必要な情報を盛り込んで話を起こします。
「承」で、その状況を進めます。
「転」で、状況がひっくり返ります。主人公の気持ちが変化します。
「結」で、話がまとまります。
最初は漠然とした思いつきであっても、「誰が、何をする」「何が、どうなる」と紙に書くと、イメージが具体的になります。
メモ書きでかまいません。また順番に書いていく必要はありません。ある程度書けたら、この起承転結を視覚的に考えていきます。
(話がトントンと進むようなとき、1シーンをいくつかに分けることがあります)
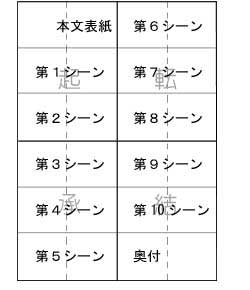
A4のコピー用紙を、話の長さによって10分割、12分割、長い話だったら16分割くらいにすることもあります。
「本文表紙」(本文=ホンモンと読みます)というのは本の中表紙のことで、シーンの欄が足りない時は、ここから第1シーンとしてもかまいません。
起承転結表とシーン割り表は、ほぼスライドしています。
「転」の後半、このシーン割だと第8シーンあたりがクライマックスです。「起・承」の各シーンは、この第8シーンをより効果的に見せるための布石です。
また、ハッピーエンドをよりハッピーに見せるには、第5シーンあたりを「どん底」にするのが常套です。
シーン割の配分はいつも一定ではなく、長い話の場合、「承」の部分のシーン数が多くなります。

写真は、10シーンの絵本のシーン割り表です。各コマの中に、ラフな絵やキーワードを書き込んでいます。本来、人に見せるものではないので、相当雑な書き方をしています。
細かい字でいっぱい書くことになるので、見にくいのですが、1枚の紙に話の流れを書き込んで、全体を一目で見渡せるようにすることが大事です。と、私は思っています。
シーン割り表は、一つの話がまとまるまでに何枚も書き直します。消しゴムで消して直すのではなく、変化が残るように何枚も書き直すと良いです。
納得がいくシーン割りが出来たら、ダミー本作りに取りかかります。
でも、せっかく作るのだから、できるだけ完成度の高いものを作りたいですよね。
少々面倒なことも言っていますが、好きな絵本を思い浮かべて、
説明を読んでいただくと、分かりやすいかも知れません。
やはり起承転結
物語作りの基本は、やはり起承転結だと思います。私が絵本講座で行っている方法を紹介します。
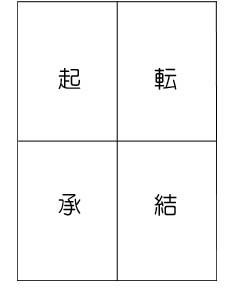
A4のコピー用紙を4つに折って、図のように配分します。
「起」は、話の発端です。物語の舞台や登場人物の紹介など、必要な情報を盛り込んで話を起こします。
「承」で、その状況を進めます。
「転」で、状況がひっくり返ります。主人公の気持ちが変化します。
「結」で、話がまとまります。
最初は漠然とした思いつきであっても、「誰が、何をする」「何が、どうなる」と紙に書くと、イメージが具体的になります。
メモ書きでかまいません。また順番に書いていく必要はありません。ある程度書けたら、この起承転結を視覚的に考えていきます。
シーン割り
絵本の見開き左右の2ページを1シーンとして、シーンで話の構成を考えます。(話がトントンと進むようなとき、1シーンをいくつかに分けることがあります)
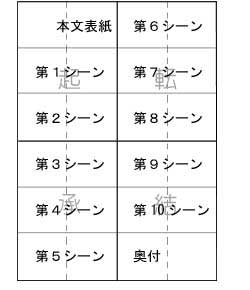
A4のコピー用紙を、話の長さによって10分割、12分割、長い話だったら16分割くらいにすることもあります。
「本文表紙」(本文=ホンモンと読みます)というのは本の中表紙のことで、シーンの欄が足りない時は、ここから第1シーンとしてもかまいません。
起承転結表とシーン割り表は、ほぼスライドしています。
「転」の後半、このシーン割だと第8シーンあたりがクライマックスです。「起・承」の各シーンは、この第8シーンをより効果的に見せるための布石です。
また、ハッピーエンドをよりハッピーに見せるには、第5シーンあたりを「どん底」にするのが常套です。
シーン割の配分はいつも一定ではなく、長い話の場合、「承」の部分のシーン数が多くなります。
シーン割り表を書こう

写真は、10シーンの絵本のシーン割り表です。各コマの中に、ラフな絵やキーワードを書き込んでいます。本来、人に見せるものではないので、相当雑な書き方をしています。
細かい字でいっぱい書くことになるので、見にくいのですが、1枚の紙に話の流れを書き込んで、全体を一目で見渡せるようにすることが大事です。と、私は思っています。
シーン割り表は、一つの話がまとまるまでに何枚も書き直します。消しゴムで消して直すのではなく、変化が残るように何枚も書き直すと良いです。
納得がいくシーン割りが出来たら、ダミー本作りに取りかかります。